今回はアクティブファンドの選び方について解説しておきます。
まず最初に、私はアクティブファンドをおすすめしているわけではないですよ!
なんなら効率的な資産形成においてはインデックスファンドだけで行ったほうが効率がいいと思っています。
その理由については「なぜアクティブファンドはインデックスファンドに勝てないのか?」をご参照ください。
そこまで理解した上で、「運用哲学に惚れ込んだ」や「投資を通じて社会貢献したい」といった理由でアクティブファンドに興味を持つ投資家も大勢います。
そういった場合はアクティブファンドに投資をするのもいいと思います。
しかし、アクティブファンドに投資する場合も、パンフレットの上手い言葉にのせられて、騙されないようにファンドを分析する必要があります。むしろ、インデックス以上に信託報酬が高額で、運用内容も分かりにくいため、インデックス以上に注意深く中身を吟味していく必要があります。
権威や肩書に騙されない
- 200年もの間、王家の資産を管理し続けてきた伝統ある運用会社
- 運用者は超一流大学で博士号を取得し、その道の権威
- 有名大学の資産運用にも携わり、資産運用の首席アドバイザー
運用者紹介の最初にはこうして運用会社やファンドマネージャーの権威性を示すような文言が多々見られますがこれだけで信用してはいけません。
もちろんこれらの実績は素晴らしいものですが、実際は大した役割ではなかったにもかかわらず過大にアピールしている場合があります。例え方は悪いですが、詐欺師もよく使う手口です。
また、輝かしい実績を持ったファンドマネージャーが在籍していても、名前を貸しているだけで実際の運用には直接かかわっていないということも無きにしも非ずです。
なんだか凄そうだというだけで、よく分からないファンドに投資しないでください!
余談ですが、こういう権威性に弱いというのは日本人だけじゃなく、世界中のだれもがそういう傾向にあるため、ファンドマネージャーの学歴や経歴はピカピカだったりします(特に海外)。
運用哲学と運用実績はマッチしているか
アクティブファンドを買うということは運用方針や運用哲学に共感したからだと思います。
しかし、その運用方針や運用哲学は運用実績にマッチしてますか?
運用方針や運用哲学に共感 したものの、運用実態までは確認していないという人も多いのではないですか?

そんなのどうやって確認すればいいの?
確かに個人投資家向けのレポートは情報が限られているため、細かく実態を分析することは不可能です。
また、運用の実態を読み解くのはここを見ればいいということができず、理解するためには投資家自身にも相当の投資経験や実績が必要になると思います。
しかし、これができないと表面だけ着飾ったなんちゃってアクティブファンドに高い信託報酬を騙し取られることになってしまいます。
自分自身でファンドの評価ができないのであれば、アクティブファンドは手を出さないほうが賢明だと思います。
長期で運用できるのか
アクティブでもインデックスでもどれだけ長期で保有し続けれるかが長期のパフォーマンスと綿密にかかわってきます。
しかし、流行り廃りのあるようなファンドの場合は長期保有が目的ではなく、一時のブームを掴むという考えで投資家も買っているし、運用もされてるということで数年後には繰上償還というケースも少なくありません。
あなたがアクティブファンドに手を出そうと思ったのは運用方針に惹かれたからであって短期のブームを当てるためではないはずです(もし、短期のブームを当てたいのならテーマ型のインデックスのほうが向いてると思います)。
あなたが買おうとしているそのファンドは長期で保有できるファンドですか?
新しいファンドに飛びつこうとしてないですか?
昔からあるファンドが必ずしもいいわけではないですが、長い間生き残ってる伝統的なアクティブファンドは独自の運用哲学があったりすることが多いです。
マネージャーの能力が制限されていないか
最後にいくら凄腕のファンドマネージャーでも制約がギチギチに決まっていると、高い信託報酬ぶんの超過リターンを出すことは困難になります。
なので、どうせ高い信託報酬を払うのなら、マネージャーが自由に投資の意思決定をできるファンドを買うべきだと思います。



アクティブファンドのファンドマネージャーは自由に自分の裁量で売買できるんじゃないの?
実際は全然そんなことないんですよ!
基本的にはフルインベストメントが基本だし、ファンドの評価はベンチマークに対してどれくらい勝ったかで評価されるため、常にベンチマークを意識した運用を行います。
また、ガイドラインで最大投資比率とか対ベンチマークの相対比率とかをセクターや各銘柄で決められていたり、取っていいリスク量まで制限されていたりします。
もともとはファンドマネージャーが無茶苦茶な運用をしないための制約ですが、制約がきついほどインデックスに似たような運用しかできなくなり、インデックスに近づけば信託報酬の差だけ確実に劣後するようになるので私はこの制約は小さいほうがいいと思っています。
ただし、制約が緩いということは対ベンチマークでめちゃくちゃ負けるということもあり得るということですよ!🤣
このガイドラインや制約についてもおそらく個人投資家は見ることができないと思います。
なので、実際どれくらいのリスクを取ってるかは自分で測定し、推測するしかないですね!
あ、ちなみにベンチマークについても体外的に発表されてない場合もあるし、されてても適切じゃない場合があります。ハイテクファンドなのにベンチマークはMSCIとかね💡(もちろんファンド評価用の厳密なベンチマークは別に設定されています)
この辺りも個人投資家が分析することの難易度を上げてる要因になってると思います。
テーマはマネージャーの制約になる
最近ではハイテクグロースが堅調なこともあり、次世代技術とかニューエネルギーみたいなファンドが人気を集めてますが、これもどうかと思います。前述しましたが、テーマで勝負したいならもっと安いテーマ型のインデックスファンドもあるので割高なアクティブファンドを買う理由にはなりません。
そして、このテーマによる制約もマネージャーの能力を制限する要素になります。
だって、制約がなければ、そのテーマが来ると判断すれば投資比率を上げれるし、今は時期じゃないと思えば比率を下げることができますから。テーマ型のファンドは強制的にそのテーマで勝負させられるということなので、制約以外の何物でもないと思います。
アクティブファンドの選定は難しい
どうです?
有望なアクティブファンドは見つけれそうですか?😀
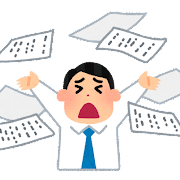
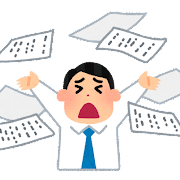
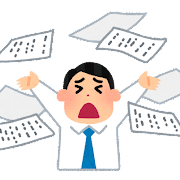
こんなに複雑なことできない!!💦
こう思う人が大半ではないでしょうか?
実は私も開示資料だけで有望なアクティブファンドを見つける自信はありません🤣
なので、投資信託のレーティング評価をしたときも、アクティブファンドはノーレーティングで返していたのです。
もちろんこれら全てをクリアしないと買う価値がないと言っているわけではないですが、これらの項目を意識しておくかどうかで少しシビアな目でファンド選定に向き合えるのではないでしょうか?
この記事がアクティブファンドの選定に少しでも役に立てばと思います!






コメント