こんにちは、やすたろ🐢です。
今回は少しお勉強的な内容です。
最近、米金利に注目が集まってます(ずっと注目はされてますが、最近特にってことですね🤣)。

米国の金利が上昇するから株式はもうダメ。今は利確のタイミング。
みなさんも、こういった意見を聞いたことがあるのではないかと思います。
では、なぜ金利が上がると株価にマイナスなのでしょうか?
さらには、金利の上昇は株価にとって本当にマイナスなのでしょうか?
今回は金利と株価の関係について解説していきたいと思います。
金利が上がると株式の期待リターンも上がる
まず受給要因で金利が上がる場合は株価にはマイナスに働きます。
受給というのは本質的には何も変わってないのに、債券の発行が活発化したとか機関投資家の購入が立て込んだなどで流通量が変化して金利が変動するみたいな場合ですね。
金利が上昇すると株式に対する期待リターンも上がります。
金利が5%のときに株式のリターンが7%より、金利が1%のときに株式リターンが7%のほうが嬉しいと思います。
金利5%の場合はリスクを取ったことに対する上乗せのリターンが2%しかないのに対して、金利1%の場合は上乗せが6%もありますからね。
このように金利が上昇すつ場合、株式に対する期待リターンも上がるため、株価に対してはマイナスに働きます。
詳しく知りたいかたはこちらもご参照いただければと思います。
金利が上がると財務不安が重くなる
また金利が上がると企業の財務負担も大きくなります。
企業はすべて資本金でまかなうわけではなく、社債の発行や融資を受けて株主価値の最大化を図ります。
金利が上がると、この社債や融資の金利も上がってしまいます。
住宅ローンを借りている人は分かると思いますが、少しの金利の変化でも家計への影響はけっこう違いますよね?😅
これらの債務比率が高い企業ほど金利の上昇によって株価へのマイナスの影響は大きくなります。
金利が上昇する理由に目を向ける



じゃあ、金利が上がると株価が下がるってことでOK?
はい、単純に金利と株価の関係をみるとそういうことになります。
しかし、少し待ってください!
金利は意味なく上下しているわけではなく、金利の変化には理由があります。
そこを無視して結論づけてしまうと、間違った答えに行きついてしまします。
金利はインフレに連動する
米国の中央銀行であるFRBの使命は雇用の最大化と物価の安定で、それらを達成するために政策金利の変更や資産買い入れ策などの金融政策を実施しています。
雇用を最大化するためには企業が事業拡大しないといけません。新しい事業に取り組み、人を雇うことで雇用が最大化していくのですから。そして金利が低いと企業は資金調達しやすくなるため、中央銀行はなるべく金利を低位にしておきたいというインセンティブが働きます。
しかし、物価を安定させるためにはそうは言っていられません。
物価が上昇、インフレが起きているのに金利を低位で保ったままいるとインフレが加速して経済が混乱し、さらには社会秩序の崩壊につながりかねません。なので、中央銀行は行き過ぎたインフレを抑止するために金利を引き上げる政策を打ちます。
各国中央銀行によってスタンスの細かな差はありますが、どこの中央銀行もインフレには目を光らせてます。
また、市場参加者にとってもインフレが進行しているなかでの低金利債券なんでだれも見向きもしないため、債券価格は下落し、結果金利は上昇することになります。
インフレ3%の場合に利回り1%の債券を持っていても、実質ベースでみると▲2%ずつ減価してしまうでしょ?
なのでインフレ3%であれば利回りも3%以上ないと投資する意味がないということです。
インフレには良いインフレと悪いインフレがある
先ほどはインフレについて少しネガティブなトーンで書きましたが、インフレには2種類あります。
良いインフレと悪いインフレです。
良いインフレ下では、需要が強いことで製品価格が上がります。その結果、企業は儲けが増え、また労働者の賃金も上がることでさらに次の需要を生む、というように景気拡大を伴う正のループが発生します。需要が物価を引き上げることからデマンド・プル・インフレという言い方もできます。
悪いインフレ下では、原材料価格の高騰により製品価格が上がります。この場合は、十分な値上げができず企業の利幅が縮小することで企業の儲けは減少し、社員の給料も上がりません。給料が上がらないのに物価だけ上がっていくことから、ますます需要は減っていくという悪循環を招いてしまいます。こちらは原材料価格が物価を引き上げることからコスト・プッシュ・インフレと呼ばれることもあります。
インフレの理由によって株価は反対の動き方をする
もう言いたいこと分かりましたよね?😊
良いインフレ下では、景気拡大によって企業の業績に拡大が見込まれます。また、インフレによって企業が保有している資産価格も上昇が見込まれることから、期待リターンの上昇や財務負担が重くなったとしても総合的にみると株価は上場しやすいと言えます。
逆に悪いインフレ下では、業績も低迷と金利の上昇というダブルパンチによって株価は下落しやすいと言えます。
米国で関心を集めているインフレについても、最初はコロナ後に需要が急回復したせいであり、急激な物価上昇は一時的、そしてこれは良いインフレだというふうにとらえられてました。その結果、これまで低金利によるバリュエーション面での恩恵が大きかったハイテク関連などのグロース株の上昇は鈍化しましたが、一方で景気拡大により業績拡大が期待される景気敏感株の多いバリュー株については注目を集めるようになりました。
しかし、物価の上昇が止まらず、これは悪いインフレにつながるのではないかという警戒感が高まったことで、バリュー株の上昇は短命となり、その後は株式市場全体が低迷しているという流れかと思います。
悪いインフレ懸念が広まってるなら今は利確のタイミング?



じゃあ、やはり悪いインフレへの警戒が高まっているのなら今は売り時じゃないのか?
そんな単純な話ではありません!
確かに今はインフレがとまらず、テーパリング終了や利上げ開始というのがそこまで迫っています。
しかし、警戒感が高まっているということは、引き締めは既に市場に織り込まれているため、予定通り引き締めが始まったとしても株価には影響がないということです。
もしインフレが想定より加速していくようなら株価のもう一段の下落というのもあり得ますが、逆にインフレ進行に陰りが見え始めると引き締めペースが想定より遅くなることでハイテク関連がもう一度上値を追いかけるということも十分考えられます。
なお、この市場の想定というのはその辺にいる人を適当に集めてというのではなく、市場のプロたちの総意ということもできますので、想定より正確な予想をしてやろうというのはかなり困難なことですよ。
以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました!





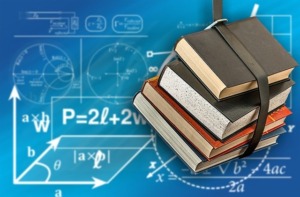
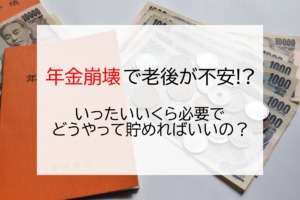
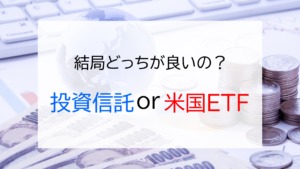


コメント