こんにちは、やすたろ🐢です。
私は日ごろから「リスク資産は株式のみでいい。リスクの量はキャッシュでコントロールすべき!」という主張をしていますが、それでも

ほとんど利息のつかない預金より、リターンは小さくても債券やコモディティに分散投資したほうが利益にはつながるのでは?
こういう意見もよく届きます。
今回はなぜ債券やコモディティへの投資が不要なのかということを定量的に示した上で、私が不要だと主張している理由を解説していきます。
分散投資の効果
まずは分散投資の効果について説明していきます。



ある程度勉強した人はまたかというような内容ですが、ここを理解してないとこの後の話すべて分からないので一応ね😅
本題ではないのでササッといきますが、以下の株式Aと株式Bの2つの株式を使ってリスク対比のリターン(要は傾き)の最大化をは計ります。
- 株式A:リスク30%、リターン15%
- 株式B:リスク20%、リターン5%
下図は株式Aと株式Bの合わせて100%のポートフォリオを10%ずつ比率を変えてプロットしたものになります。


単体でみると株式Aのほうがリスク対比のリターンが高くみえますが、図にように株式Aと株式Bの動き方次第では適度に株式Bを混ぜたほうがリスク対比のリターンは高くなります。
このときの上振れぶんが分散効果ということです。
そしてこの株式Aの動きと株式Bの動きがバラバラに動くほど分散効果は高くなります。このどれくらいバラバラで動くかというのを指数化したものが相関係数です。相関係数は完全に同じ動き=1から完全に逆の動きー1までで表されます。



相関係数が-1に近いほど分散効果は高くなります!
余談かもしれませんが、ここでいうリターンとは期待値の話です。
個別株への集中投資はハイリスク・ハイリターン、分散投資はミドルリスク・ミドルリターンと思っている人がたまーーにいますが、個別株投資はリスクが軽減されてないため、上振れも大きいだけであって期待値としてのリターンは分散投資と変わらないです。
言ってしまえば、分散投資がミドルリスク・ミドルルターンなら個別株投資はハイリスク・ミドルリターンになります。
債券を組み入れる場合
さて、ここからが本題です。



債券のリスク対比リターンが株式より劣っていたとしても分散効果があるなら債券も組み入れる価値はあるんじゃないの?
それでは実際に株式と債券の比率を上記のように変更しながら確認したいと思います。
前提として、株式と債券の相関は三菱UFJ国際投信、リスクリターンはりそなグループのデータを参考にしました。




ただ、リスク・リターンについては過去データの平均をそのまま使うことに違和感ありありなので、今の低金利環境と為替の変動も加味しつつ私の主観で以下のような前提に修正しました。


株式はみんな大好き全世界株式を前提にしています。
海外債券は先進国の国債、国内債券は日本の国債です。
リターンの低さが気になるかたはこちらも合わせて参照していただければと思います。





また、けっこう複雑な話をしているので、難しくてよく分からないという人は今は無視してもらってもけっこうです😅
上の前提を基に、債券と株式の比率を10%ずつ変更しながらプロットしたものが下図です。


まずブルーの海外債券と株式を組み合わせたポートフォリオはグレーのキャッシュと株式を組み合わせたポートフォリオより著しく劣後しているのが分かると思います。
なぜなら、海外債券のリスクのほとんどは為替のリスクでリターンにつながっていないから。また、全世界株式も外貨がほとんどなので相関係数も0.743と高く(この相関係数は私のほうでいじってないですよ🤣)分散効果も限定的だからです。
株式と債券を組み合わせるポートフォリオは教科書通りでオーソドックスだとは思いますが、外貨建ての場合は為替リスクも意識したほうがいいかなと思います!
一方で、オレンジの国内債券と株式の場合は相関係数が低いということもあり、若干ですがグレーのポートフォリオを上回っています。
だだし、若干!
これなら少し前提が変わっただけでも結論は変わりますし、手元に現金を用意してたほうが心理的な安心度は高いと思うのですがどうでしょうか?😀
ちなみに先進国にヘッジ付外債は長期でみれば国内債券と同じような動きになります。
コモディティを組み入れる場合
また債券と同じようにコモディティについてもポートフォリオに組み入れても影響は限定的なのではないかと思っています。
コモディティというと広すぎるので、例えば金で考えてみましょう。
ひと昔前は、有事の金買いといって投資家のセンチメントが悪化した場合などに金が買われていましたが、足元では金融緩和で金も株価も同じように上昇するというように分散効果は低くなっています。
そして、金を始めとしたコモディティは何か付加価値を生み出しているわけではなく、需給で価格が決まるとするならば、インフレ率以上の価格上昇は見込めず、実質的なリターンはゼロとなります。
これらを踏まえてこんな感じで前提を作ってみました。
また、リスクについては三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド)のこちらのデータを参考にしてます。


この前提を基にプロットしたものが下図です。


相関係数次第のところもありますが、金を組み入れることで若干のリスクリターンの向上は計れるかもしれません。
だだし、こちらについても若干。
米国ETFを使って突き詰めていくというのもありですが、投資信託を使う場合は金の信託報酬はけっこう高く(前述のファインゴールドの信託報酬は0.99%程度)なるので、個人投資家は触らないというのが無難かなとは思います。
まとめ
今回は少し複雑になったので結論をまとめます。
- ポートフォリオを複雑にしたところで前提次第で吹き飛ぶ程度しかリターンの向上が図れない。
- それならば、株式だけでポートフォリオを組み、リスク量はキャッシュとのバランスで調整したほうがシンプルで管理しやすいのではないか?
以上になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。





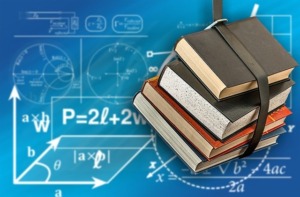
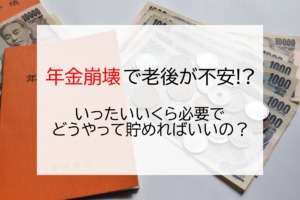
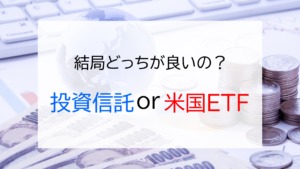


コメント